
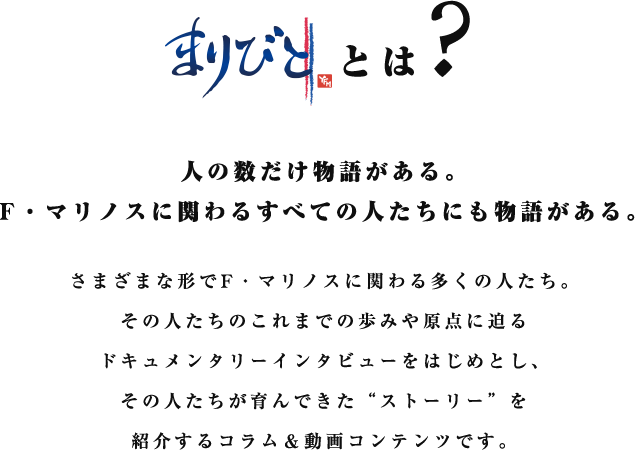



守備では最後の砦、攻撃では最初の一手。
アンジェ・ポステコグルー監督が実践する「ハイプレス・ハイライン」において、ゴールキーパーは大役を担う。広大なエリアをカバーするとともに、意図あるパスから「つなぎ」が始まる。31歳、プロ14年目の飯倉大樹は、まさにそのはまり役となっている。
積み重ねてきて、今がある。
苦しんできた。悩んできた。
プロ1年目の絶望、片道切符と思い込んだJFLへの移籍、先輩ゴールキーパーとの熾烈なレギュラー争い、そして病気……。
いずれも乗り越えてきた。いずれも飯倉を成長させる肥やしとなってきた。
苦しんで、悩んで、乗り越えて、成長して。ようやく彼は、ある境地にたどり着いた――。

とんがっていた。
いや、そうしないとひるんでしまいそうだから。
プライマリー追浜、ジュニアユース追浜、ユースと横浜F・マリノスの育成組織で育ってきた飯倉はトップチームがリーグ2連覇した翌年の2005年に加入した。
「自分の肩書きがプロ選手になったとはいえ、もう周りのメンツが凄すぎて……。自分なんて豆粒みたいな感じで、勝ち目がないからハッタリでもかまさないと保てない。生意気言ったり、サッカーの本質とは違うところに少し向いてしまったのが1年目でした」
練習に行くのも、億劫だった。周りのうまさについていけないと感じた。張り詰めた緊張感が漂う練習の中、先輩たちに話しかけられない雰囲気もあった。せめてもの意地が自分を大きく見せること。しかしそれはストレスにもなった。サッカーに打ち込めない自分がいた。自己評価は低かった。
「よくプロになれたなと思うぐらい下手くそでした。フィードは得意だとしても、ゴールキーピングに関しては、たとえば20ぐらいないとプロになれないところ、僕は2とか3とかそのレベルだと思っていましたから」
プロになっただけ。飯倉は希望よりも失望の日々を送っていた。
そんな自分を可愛がってくれる、先輩がいた。2連覇に立役者となった奥大介さんだった。食事もよくごちそうになった。ジュビロ磐田の黄金期や、F・マリノスの2連覇の話を聞かせてくれた。そして決まって「大さん」は、顔を向けてこう言ってくれた。
「ヒロキ、花咲かせろよ。プロは花咲かせてナンボやぞ」
奥の前では、とがらなくて良かった。素のままの自分でいることができた。

翌年、当時JFLに昇格したばかりのロッソ熊本(現ロアッソ熊本)への期限付き移籍が発表された。望んだ移籍ではなかった。チームの評価は高くないと感じ、これは期限付きから完全移籍に移行する片道切符だと覚悟した。しかしそのとき、奥が強化部に「ヒロキを必ず1年で戻してほしい」と掛け合ってくれたことを知った。感謝の言葉もなかった。
「大さんの顔に、泥は濡れないと思いました。みんなレベルが高いし、僕の帰ってくる場所なんてなかったと思うんです。それでも大きい壁に挑むために努力しなきゃって」
熊本ではホームシックにもなった。
寮の周りには街灯ひとつなく、引っ越し作業中に配線がなくなってテレビすら見ることもできない。3日間練習して1日オフの3勤1休が基本的なスケジュール。オフ前日の練習が終わると飛行機で横浜に戻り、翌日にまた熊本に戻る生活が続いた。向かう先は、決まって奥先輩の自宅。励まされ、ハッパを掛けられた。そしていつしか横浜に戻らなくても大丈夫になった。
最初は試合に出ることはできなかったが、一度チャンスをつかんでからは離すことはなかった。ハングリーな環境でひたむきにサッカーに取り組む周囲のチームメイトにも刺激を受けた。

頑張ることはカッコ悪くない。むしろカッコいい。努力することの大切さを肌で知った「サッカー人生で一番の転機となった」1年になった。
横浜に戻ってきた。
2007年はみなとみらいのマリノスタウンがオープンし、自分の新しいサッカー人生が本格的にスタートする思いがした。横浜FCに移籍した奥に対して、成長を見せることが恩返しだと感じた。
榎本哲也が正GKに君臨し、キャリアのある高桑大二朗や1つ年下の秋元陽太もいた。切磋琢磨の中で「2、3」だったゴールキーピングの技術は10ぐらいに引き上がった感覚を持つことができた。10月の清水エスパルス戦でJリーグデビューを果たした。


あの場にはきっともどれない。もう、やめよう。また引退のことが頭によぎった。
「最悪のメンタル、最悪のオーラ」のときに、松永成立GKコーチとの衝突が待っていた。怒られて、怒られて、逆に自分も思いの丈をぶつけていった。飯倉は思った。22歳で引退を覚悟したあのときも「シゲさんとぶつかった」と。そして師との衝突は、実は上向く分岐点なのだとも。
「ここまでやれたこと自体が奇跡なんです。だからもう1回努力してみようと思いました」
どん底まで落ちて、考え方も変わった。
自分よりもチームに目が行くようになった。高ぶる感情もコントロールできるようになった。2年間、出場ゼロに終わった「ストレートな守護神」は2015年から再び出場機会を増やしていく。
「クロスに対して全部出ていくとか、機動力を活かしてシュートを止めるとか、攻撃の起点になってとか全部、自分がうまくやって勝ってやろうと思ったのが昔。でもこの頃からチームを信じて任せられるようになったというか、チームに還元するその過程を大事にして勝てればいいやぐらいの感覚になったんです」
2016年はまたも榎本がポジションを奪い返し、そのまた翌年は飯倉が主にゴールマウスを守ることになる。だがそこにはライバルというものを超越した感覚が、飯倉の中で芽生えるようになっていた。
「哲くんにはない、自分にできることって何だろうってずっとやってきて、それがようやく形になってきた。哲くんがいたからもっとうまくなろうって思えたし、哲くんがいたから、自分はここまでやってこれた。前からリスペクトはしていましたけど、よりリスペクトできるようになりました。ライバルというよりも同志に近い感覚になったし、哲くんはずっとキーパー最年長でやってきて大変だったなって、本当に今になって分かることも多いんです。哲くんの存在はライバルだから面倒でしたよ、勝つためにはすっげえ大変でしたよ。でも哲くんの存在はでかかった。すっげえでかかった」
そしてもう一人、松永コーチの存在が飯倉を大きくさせた。彼には日産自動車、F・マリノスのゴールキーパーのDNAとも言える〝シゲイズム〟がしっかりと流れている。

「シゲさんもああいう(ストレートな)人なので衝突もしますけど、僕にとっては師匠だし、凄い存在。技術のみならず、周りの選手から信頼されるための振る舞いを教えてくれています。シゲさんから教わったことは本当にいっぱいあるんです。
ゴールを守ることって、本当に難しい。簡単そうなシュートでも強いスピンが掛かっていて、処理を間違ったら失点につながってしまう。ミスが起こったときでも普段の練習や日頃の生活態度でしっかり示していれば、信頼を損なわない。チームからの信頼があればこそ、僕も余計にみんなのミスを守ってあげたい。みんなが信じてくれるように、行動していくことが今の僕の立ち位置だと思っています」
真っ直ぐな目をこちらに向けて、真っ直ぐに言った。
今はF・マリノスのサッカースタイルそのものの変革期にあり、我慢の時期が続いている。しかしそれを乗り越えてこそ、得られる境地、得られる景色が待っていることを、飯倉は身を持って知っている。ゴールキーパーが新しいスタイルの先導役になるのは、まさに運命と思えてくる。ただ、あくまでF・マリノスで培ってきたものが勝負のベースにある。
「シゲさんも哲くんも俺も、身長は小さいけど、雰囲気はあるよっていうF・マリノスの系譜のゴールキーパーだと思うんです。アクティブだし、暑苦しいところもあるし(笑)。相手からしたらゴールが小さく見えるというか、そういう雰囲気を、オーラを出していきたい。そしてアンジェ監督のサッカースタイルでタイトルを獲りたい。このやり方を根づかせるために、僕自身も努力していきたい。この挑戦を自分自身楽しみたいと思って、やっています」
昔とは違う、飯倉大樹がいる。昔のままの、飯倉大樹もいる。
失望は、希望のためにある。
飯倉大樹が、それを何よりも証明している。

二宮寿朗Toshio Ninomiya
1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載
