
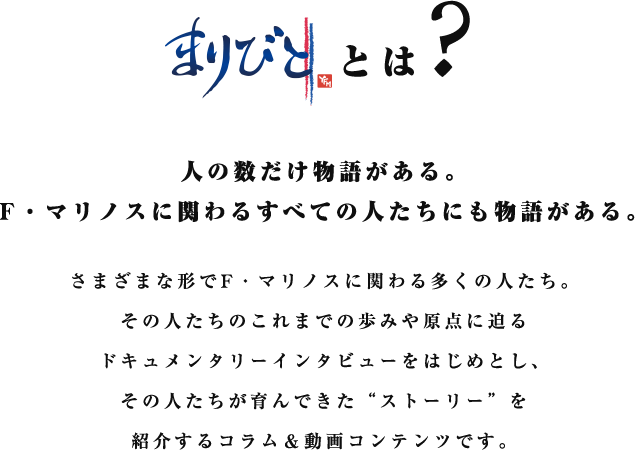



ピッチの後ろでビブスを着込み、ファインダー越しにシャッターを切る。
Jリーグが開幕した1993年から24年間、トリコロールをずっと追ってきた男がいる。70歳になっても、彼は熟練の佇まいでカメラをピッチに向けている。
横浜F・マリノスのオフィシャルカメラマン、松本正。彼はクラブの記録と記憶を撮り続けてきた。

オフィシャルの仕事は試合のシーンを切り取れば終わりではない。宣材写真や様々なグッズ商品やクラブの出版物に使用する写真など、そのリクエストは多岐に富む。
大変な仕事ですよね?
そう水を向けると、ベテランカメラマンはにこやかに笑う。
「いやいや、もう20年以上もやっていますからね。クラブがどういう写真を欲しがっているかを、常に頭には入れています。会場に足を運んでくれたお客さんに渡すものだから集合写真でいいものを撮ろうとか、商品用に使うものだから選手のワンショットをしっかり撮っておこうとか。一方で、臨場感ある試合の雰囲気も撮りますよ。まあカレンダー用とか出版物に使うとなるとちょっと燃えたりもしますね」
無理な注文もあったのではないですか?
興味ついでにもうひとつ尋ねると、ひそやかに笑う。
「困ったというのはあったかな。アウェーでサポーターが応援する、いい雰囲気の写真を試合の1時間前に送ってほしいというリクエストがあったんですよ。でも1時間前だから、サポーターのみなさんもまだ準備しているじゃないですか。さすがにいい雰囲気のものを撮れなくてね。まあ頑張ってやってみたけど、どうでしたかねえ」
〝無理だよ〟と断るのではなく、〝やってみますよ〟とトライする。飄々と語る姿に、彼の矜持をみる思いがした。
松本が20代のころである。
彼はスタジオカメラマンとして生計を立てていたが、1966年に刊行した「サッカーマガジン」の編集者と知り合い、JSL(日本サッカーリーグ)の試合を撮影するようになったのが始まりだった。

1973年、彼に予期しなかった依頼がサッカーマガジンから舞い込む。イタリアのセリエAを撮ってきてほしいと頼まれたのだ。セリエAでプレーしている選手など誰一人も知らなかったが、「やってみましょう」と引き受けてしまう。サッカーマガジンに紹介された欧州サッカーに詳しい大学生との過酷な男2人旅となった。
「〝撮ってきて〟と頼まれたとは言っても、取材申請のやり方すら分かりませんからね。イタリア語も分からない。とりあえずサッカーの専門紙を買って、対戦カードを見るんです。その大学生の古田くんと相談して、このカードにしようと決めたら場所を確かめて、試合の1週間前に現地に行ってみる。何とかそこでクラブの事務所を探しあてて、取材の交渉を2人でやりました。自分たちの英語もたどたどしくて、相手だって急に突撃で来られるわけですからね、びっくりしたとは思いますよ」
大変だったのがACミランとインテルのミラノダービー。最大の人気カードに、直接交渉は通用しなかった。困っていたら、助け舟がやってきた。専門紙の記者らしき人が「せっかく日本からやってきたんだ。許可してあげてよ」と後押ししてくれ、取材許可が下りたのだった。記者に御礼の言葉をのべ、松本はサンシーロのピッチに入った。
ウォーッ! ワーッ!
JSLでは、いや日本のスポーツでは体験したことのない、圧迫感、威圧感がそこにはあった。7万人の大観衆が試合前からボルテージを上げていた。カメラを握る手が、震えていた。自分も気持ちが高ぶっていくのを感じていた。
「もうお祭りでしたね。あの雰囲気は忘れられません。ワクワクするというか、自分も撮りながらエキサイトしていましたから。インテルの(アレッサンドロ・)マッツォーラはテクニックがあって、カッコ良かったなあ」
この体験が「サッカーをもっと撮りたい」という願望に変わっていく。松本は帰国後、ラグビーとサッカーを撮るスポーツカメラマンとして活躍し、ワールドカップも74年西ドイツに始まり、何大会にもわたって現地に赴いて撮影している。1年ほどロンドンを拠点に、欧州サッカーを追った時期もあった。日本でもサッカーが次第に盛り上がるようになり、松本も忙しい日々を送るようになっていた。
Jリーグに移り変わろうとしていたタイミングで、松本のもとに連絡が入った。
「横浜マリノスのオフィシャルカメラマンに興味ありませんか?」
それがマリノスとの運命の出会いだった。
まずはやってみる。それが松本のスタンスである。
Jリーグが始まったばかりで、オフィシャルがどんな仕事なのかも分からない。それでも持ち前の好奇心が上回った。
被写体として魅力的に映ったのが、背番号10を背負う木村和司だった。
「(ヨハン・)クライフ、(フランツ・)ベッケンバウアーを見ても、素晴らしい選手というのはオーラがありますよね。日本で言えばヤンマーの釜本邦茂さん。背番号9と一体になっていて、後ろ姿でも釜本さんだとはっきり分かる。だから後ろ姿もバンバン撮りました。同じ意味で、和司さんにはまとっているオーラを感じました」
93年5月15日、ヴェルディ川崎とのJリーグ開幕戦に、あのときミラノダービーで感じたような「祭り」を感じた。そう「祭り」の始まり。まさか日本にこんな時代が訪れるとは、夢にも思わなかったという。
あれから24年。マリノスのどの試合が一番心に残っているのか。
松本は意外にも「開幕前のあの試合」を挙げた。それも即答で。
93年4月16日のアジアカップウィナーズカップ決勝戦第2戦。イランのピルズィ(ペルセポリスFC)を相手にホームで1―1と引き分け、イランに赴いて第2戦に臨んだ。10万人以上の観客で埋めつくされたスタジアム。「あんな異様な雰囲気は初めての経験でしたから」と松本は目を丸くして言った。
「試合前、危ないからと言われて選手と一緒にマイクロバスでグラウンドの中まで入ったんですけど、外から見えないようにカーテンを閉め切っての移動でした。コツコツ音が鳴っていましたから、小石をぶつけられていたんじゃないですかね。試合は防戦一方でしたけど、神野(卓哉)くんがヘディングで最後にゴールを奪って優勝したんです。そうしたら怒ったファンが爆竹を鳴らしてね。選手も僕も危害が及ばないようにってピッチの中央に集まって、そこで記念撮影してからバスに乗り込んで帰ったんです。窓の外はコツコツと鳴る音が一段と凄くてね。でも優勝したからみんな明るい雰囲気でね。あのときのことは今もハッキリと覚えています」



印象的な試合の次は、印象的なプレー。
これも即答だった。〝ドラゴン〟久保竜彦のジャンプ力は、想像をはるかに上回っていたという。
「長玉(望遠レンズ)を使って久保くんを撮ると、首が切れていたりするんですよ。僕の目測よりはるかに上まで飛んでいる。いや凄いね。久保くんのジャンプを長玉で撮るのは凄く難しかった記憶がありますね」

95年のJリーグ初制覇、01年のヤマザキナビスコカップ初優勝、03年04年のリーグ2連覇、14年の天皇杯優勝……そこにはいつも歓喜の姿を切り取る、松本がいた。
気がつけば、20年以上。好奇心は昔も今も変わらない。
「こんなに長くやるとは思ってもみませんでしたね。ここまで続けられているのは広報をはじめ、クラブの方のご理解があるからだと思います。ファインダー越しに選手のみなさんの喜怒哀楽を見ていますから、うれしいだろうなとか、苦しいだろうなとか感情移入しながら撮っています。できることなら、体力が続く限りはやりたいという思いがあります」
記録と記憶を、切り取る喜び。
ベテランのカメラマンは晴れやかに笑った。

二宮寿朗Toshio Ninomiya
1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載
