
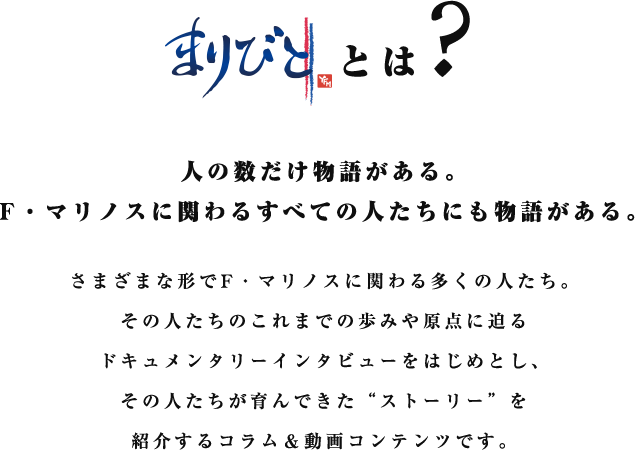



あのときも雨が降っていた。あのときもゴールキーパーが退場した。
2019年12月7日と2003年11月29日、ともに日産スタジアム。前者は15年ぶりのリーグ制覇を果たし、後者は8年ぶり。オールドファンならきっと16年前の情景を思い浮かべたに違いない。
あのときも超満員で埋めつくされた。あのときも熱狂した。
2019年12月7日と2004年12月5日、ともに日産スタジアム。前者はJ1最多の6万3854人、浦和レッズとのチャンピオンシップ第1戦の後者はJ公式戦最多の6万4889人。熱烈なサポーターなら15年前の光景を胸に呼び戻したに違いない。
2連覇以来となるリーグ制覇。
あのときの強いF・マリノスを率いたのが日本代表を初めてワールドカップに導き、初めてワールドカップの舞台に立った岡田武史監督であった。勝つ集団に変貌させた〝中興の祖〟が語る、昔のF・マリノスと今のF・マリノス――。

当時、岡田のF・マリノス監督就任は大きなニュースとして扱われた。
2002年の日韓ワールドカップで日本代表は初めて決勝トーナメントに進出し、Jリーグも再び盛り上がりを見せようとしていた。コンサドーレ札幌をJ2優勝に導き、J1残留を果たしたことで退任した岡田はワールドカップを勉強の場として〝浪人〟し、次の仕事先に注目が集まっていた。
FC今治の会長に就任して5年目。ようやくJリーグ入会をつかんだ人は、経営者になっても勝負師のオーラを漂わせる。F・マリノス監督就任の経緯を懐かしそうにこう振り返った。
「もちろん、覚えているよ。日韓ワールドカップを充電期間にさせてもらって、翌年からまた(監督を)やろうと思っていた。札幌時代には単身赴任もした。ただ家族からは別々に生活をするのはやめようと言われていたし、俺もそうだなと思った。いろんなクラブからオファーをもらったなかで、自宅から一番近いF・マリノスにした」
そうは言うが、それだけで動く人ではない。
新しいチャレンジに何か感じたものが、きっとあったからだ。

松田直樹、中澤佑二、波戸康広、奥大介、遠藤彰弘……日本代表クラスを多くそろえながらも優勝をつかみ取れない時期が続いていた。岡田の就任1年目に久保竜彦、佐藤由紀彦らも加入。チームに対する最初の印象は「確かにみんなうまい。だけど勝つことに対する執着心は薄いと感じた」。ロッカールームをきれいにさせ、練習でも最後までやり切るよう「勝負は細部に宿る」と口酸っぱく言い聞かせた。規律、帰属意識、執着心。意識改革からそれは始まった。
開幕戦は前年覇者・ジュビロ磐田とアウェーでの一戦。
スターティングのボランチには中心選手の一人である上野良治ではなく、プロ2年目の那須大亮を抜てきした。彼の本職はセンターバック。先入観を持たない岡田の一手は、チーム内外に驚きを与えた。
「ヨシハルとは話し合った。使いたいとは思っていたけど、アイツのところでテンポが遅れてしまうのが俺はどうしても嫌で、こういうプレーをしてくれって何度か伝えた。最終的には『やらないんだったら、使わない』と。するとアイツも『じゃあ自分は向いていないですね』って言ってきてね。みんなポリシーを持ってプレーしているのは分かる。これはヨシハルだけじゃないけど、これまでのプレースタイルを変えてくれと言っても簡単じゃないなというのは最初の鹿児島キャンプのときから感じていたこと。
ヨシハルの代わりに那須を使ったのは隣が攻撃に出ていくアキ(遠藤)だったから、守備になったときにつぶせるヤツがいい、と。練習でも中盤でつぶせずにディフェンスラインまでスーッと来られてしまうことが多くて、ワンストップさせたかった。那須はボランチをやったことないって言っていたけど(笑)」
ジュビロとの開幕戦は、ボランチの遠藤が先制点を挙げ、続けて佐藤が2点目を奪う。打ち合いとなったゲームを4-2で制し、最高の船出を切ることができたのだった。
「注目されているのは分かっていたし、どういう試合になるかでこれからにもかかわってくる。もの凄く大きなポイントとしてあの開幕戦を捉えていた。俺が求めるプレーをみんな納得して能動的にやってくれていたとは思う。球際の厳しさ、闘う姿勢とか基本的なことなんだけど、それをレベルの高い選手がやるわけだから。勝負に対する執着心はもの凄く強くなっていったと感じていた」
ファーストステージを制し、セカンドステージも逆転優勝の可能性を残して首位ジュビロとの最終戦を迎えた。雨のホームゲーム。開始2分でグラウに先制ゴールを奪われ、GK榎本哲也は退場。ハーフタイムを0-1で折り返した。
岡田はあのときの記憶を呼び起こす。口調がちょっとだけ早くなる。
「先制されて1人少ない状況で、相手はあのジュビロ。後半に1点を返しても、相手は引き分けで優勝できる状況だったんだよ。もし我々が後半の早い時間帯で2点取ることができたら、逆にジュビロの総攻撃を食らって持ちこたえられない。手は一つしかないと思った。ハーフタイムに『何とか1点とって、残り10分間に入るまで耐えろ』と伝えた。『最後の10分に入ったら、相手の心理とすれば守り切りたいと思うようになる。そうなると逆に攻めてこない。そこから何点取られてもいいから、怖がらずに前に行け』とね。まあ、それでもうまくいかなかったなと思っていたら、あのタツ(久保)の1本が……」
勝負師の勘だった。
後半5分にマルキーニョスのゴールで追いつき、そこからは岡田の指示どおりに耐えた。松田からポーンと蹴り出されたボールはピッチに大きく弾んだ。ラストチャンス。落下のタイミングに合わせた久保のヘディングシュートが決まる。他会場の鹿島アントラーズも勝ち点3を積み上げられず、奇跡の両ステージ制覇を達成する。まさに選手たちが勝負への執着心を出し切ってもぎ取った栄冠であった。

就任2年目はファーストを制して3ステージ連続優勝を果たしながらもセカンドは6位にとどまった。しかもレッズとは勝ち点14も引き離されている。
岡田の回想――。
「レッズは調子良かったし、セカンドステージで勝ったチームがチャンピオンシップも大体、制していた。やることは一つ、エメルソンを抑えて勝つ。その作戦をチームに落とし込んだんだけど、ホームでの第1戦はそこまでやるつもりはなかったんだ。泥臭く何とか頑張ってスコアレスに持ち込むくらいでいい、と。(作戦を)使うなって言ったのに、アイツら全部出しちゃったんだよ(笑)」
超満員のホームが選手たちを後押ししたのか、躍動がピッチにあった。前線からの連動したプレスと後方の押し上げでエメルソンに仕事をさせず、パターンを増やしていたセットプレーから点を取って1-0で逃げ切った。
だが指揮官は頭を抱えていた。
「手の内をすべて出してしまったから、ウチはプラスアルファがもうないんだよ。ギド(・ブッフバルト)は手を打ってくるだろうしね。弱ったなと思ったんだ。でもあの1週間はとにかく練習の雰囲気が素晴らしかった。厳しさがあって、笑顔もあって、みんな活き活きとしていた。負ける気はまったくしなくなった」
今度は逆に、真っ赤に染まったアウェーの埼玉スタジアム。
後半に入って中西永輔が退場し、そこで与えた直接FKを三都主アレサンドロに決められた。これで2戦合計1-1。延長戦に入る前、岡田は選手たちに敢えて何も伝えなかったという。

「いつもなら戦術的な指示をいくつか出す。でもこのときは何も言う必要がなかった。『頑張れよ』って確かそれくらい。後で樋口(靖洋コーチ)に聞いたら、俺が何も言わなかったから選手たちはザワついていたらしい(笑)」
120分間では決着がつかず、最後はPK戦を制してリーグ2連覇を果たした。
岡田体制2年目は韓国代表・安貞桓、中西、田中隼磨らがチームに加わっていた。新戦力ではないが、もう一人忘れてはいけないのが上野である。2003年は4試合の出場にとどまっていたが、このシーズン、岡田は主力として上野を起用した。
「1年目が終わったときに、ヨシハルには、移籍したいならそうしてもらって構わない。こちらも協力できるところは協力する、と伝えた。でもアイツのほうから『もう1年やらせてほしい』と。こだわっていた自分のプレースタイルを変えてきた。2年目の優勝はアイツのおかげだと今でも俺は思っている」

フラットな競争も岡田F・マリノスの強みであった。安泰な者など誰もいない。レベルの高い競争が、チーム全体の底力を引き上げていた。これは今のアンジェ ポステコグルー体制とも共通する。
劇的な2連覇を果たした岡田に、今回の15年ぶりのリーグ優勝はどのように見えたのだろうか。
「2年目の2004年シーズンは最初、結果が出なかった。同じことをやっても面白くないと思って選手にある程度、やり方を投げた。極端に言うなら、好きなようにやれ、と。でもこのままやっていたら降格もあると思って、元のやり方に戻した。戻すことで、勝っていけることも見えていた。でも去年のF・マリノスはどうだったか。うまくいっていない時期であっても、ポステコグルーは(やり方を)変えなかった。俺だったら勝つほうに切り替えていたと思う。うまくいかないときにそれを続けることがいかに勇気のいることか。
それが今シーズンに活きたということ。監督に言われて、無理やりやっているサッカーじゃない。全員が活き活きしてサッカーをやっている。本当に素晴らしいチームだよ。俺のときはスタイルを確立して優勝できたわけじゃないから。今のチームにはそれがある。このクラブは、洗練された都会のチームでなければならない。F・マリノスらしく優勝したことに心から敬意を表したいと思う」
岡田は2006年のシーズン途中、成績不振の責任を取ってチームを去った。その後、日本代表監督に再び就任し、2010年の南アフリカワールドカップでは低評価を覆して決勝トーナメントに進出した。
岡田の長い指導者キャリアにおいて、F・マリノス時代はどんな経験値を得ることができたのだろうか。
勝負師の目に力が入った気がした。
「F・マリノスでの自分がなかったら、今の俺はなかったんだろうな、多分。勝っていなかったら、評価もされていなかっただろうから。思い浮かぶのは6万人以上のお客さんが入った(チャンピオンシップ第1戦の)あの光景。これは忘れられない。今でも忘れられない」
あのときがあったから今がある。
岡田武史のF・マリノスがなかったら、きっと今のF・マリノスはなかった。

二宮寿朗Toshio Ninomiya
1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載
