
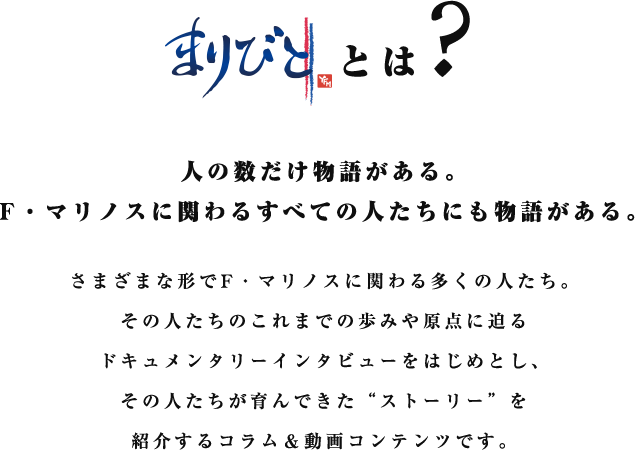



叩き上げの育成コーチである。
横浜F・マリノスのジュニアユース(U-15)監督を務める坪倉進弥は、日産FCジュニアユース、横浜マリノスユース出身で、法政大学を中退して21歳で指導キャリアをスタートさせてからはや20年が経った。それもF・マリノス一筋で。
これまで栗原勇蔵、飯倉大樹、天野純、山田康太、大橋正博、金子勇樹、石川直宏、坂田大輔、谷口博之、ハーフナー・マイク、齋藤学、小野裕二ら多くの選手をトップチームに引き上げてきた。育成年代の選手たちの「個」を伸ばす指導力には定評がある。昨年はJFA・Jリーグ協働プログラム(JJP)の一環でベルギー1部アンデルレヒトのアカデミーに1年間派遣され、考え方や指導者としての幅も広がったという。
F・マリノスが生んだ育成のスペシャリストは当初、指導者志望ではなかった。天職との巡り合わせには、多くの先輩〝まりびと〟との出会い、教えがあった――。

言わば無職の状態だった。
サッカー推薦で入った法政大学を1年で退学。20歳を目前にして、坪倉は一度サッカーから離れることを決断した。
「腰を長らくケガしていて、大学のサッカー部に入ってプレイヤーとしての自分の先が見えちゃった気がしたんです。ちょっと人生を考え直してみたいなって」
マリノスからの推薦入学だったため、坪倉は怒られることを承知でユースの坂木監督(現日本工学院サッカー部テクニカルダイレクター)のもとを訪ねた。しかし待っていたのは怒鳴り声ではなかった。
「もしサッカーにかかわりたいというなら、いつでもウチに来ればいい」
その言葉が坪倉の耳にこびりつく。大学を辞めて、バイトで貯めたお金で青春を謳歌しようとした。だが友人と遊んでも、自由に時間を使っても満たされない。そのような生活は半年で飽きてしまった。
サッカーにかかわりたい。何でもいい、俺がずっと育ってきたマリノスにかかわる仕事がしたい。
その衝動を抑えられなくなり、大学を中退して1年も経たずにもう一度、坂木監督(現日本工学院サッカー部テクニカルダイレクター)に会いに行き、頭を下げて自分の思いを伝えた。
すると、またしても意外な答えが待っていた。ジュニアユースの監督を呼びつけ、「ツボが仕事をしたいというから、面倒みてやってくれるか」。アルバイト契約ながらその場で採用され、かつ、スコールコーチとジュニアユースのアシスタントコーチに入ったのだった。

指導者を目指すつもりもなかったが、仕事にのめりこんでいく自分がいた。
「僕はジュニアユース、ユースとここで学んできたはずなのに、立場が変わると〝コーチは、こんな工夫をしていたのか〟と分かったんです。安易な考えを持って教えちゃいけない、大変な仕事なんだなって思いましたね」
駆け出しのコーチ見習いは、年の近い中学生たちのいいお兄ちゃん的な存在になっていく。自分なりに熱心に指導し、子供たちの相談にも乗るようになっていた。そんな坪倉の姿勢を見ていたのか、2年目に入ると育成ダイレクターの木村浩吉からユースのアシスタントコーチに入るよう要請される。
しかし坪倉は頑なに拒否した。
「ユースの選手は、僕と年もあんまり変わらないし、何より自信がないですからね。〝無理です〟と何度断っても、浩吉さんは〝いいからやるんだ〟と。でも今思うと、98年からユースのアシスタントに入ったことが、すごく自分にとっては大きな経験になりました」
ユースでは98年に樋口靖洋監督、99年に中田仁司監督、00年に安達亮監督といずれものちにJ1で監督を務める指導者のもとで働いた。
強烈に印象に残っている出来事がある。
98年にクラブユース予選で横浜フリューゲルスユースと対戦したときだ。相手は坂田、田中ら1、2年生が主体で、安達が監督を務めていた。その安達の指導ぶりに驚いたという。
「アップからチームのテンションが高くて、試合中の亮さんは、もう怒ったり、わめいたり、とにかくうるさいんです(笑)。思わず樋口さんに〝あんな指導法、あるんですかね?〟って試合中に聞いたほど。でもピッチを見ていると、選手たちのテンションは下がるどころか上がっている感じで、より生き生きとしていました」
その年、フリューゲルスと合併することが決まり、坂田や田中たち、そして安達もマリノスに合流して「F・マリノスユース」となる。「絶対に苦手だと思った」安達とは不思議とウマが合った。00年にその安達がユースの監督に就任する。
「どちらかと言うと、技術的にレベルの高い子にはあまり強く指摘をしてこなかったのがこれまで。でも亮さんは逆。うまい子に対しては〝もっとできるんだろう?〟って高い要求をして、はっきりとダメ出しもする。それを何回も何回もやるんです」
安達の指導に反発する選手たちもいた。だがそのたびに坪倉は選手に言い聞かせた。「期待しているからの言葉なんだ。それを感じるべきじゃないのか」と。監督の指導法によって、コーチが柔軟に対応していくこともこの3年間で鍛えられたことだった。
「僕はそれこそ金子や栗原をジュニアユースからずっと見ているわけです。同じ素材をそれぞれの監督が違うアプローチで育てていくというのはもの凄く勉強になりました。選手たちからの反応もリアルタイムで受けるので、その指導の効果なども分かる。指導本よりも映像よりも、日々の現場が何よりの学びの場でした」
以降、ユースとジュニアユースを行き来しながらアシスタントコーチを務め、30歳になる2006年にジュニアユース追浜の監督に就任する。1年目に全日本クラブジュニアユース選手権で優勝を果たし、13年から現職のジュニアユース監督を務める。

(前列右から4番目・天野純/前列右から2番目小野裕二)
長いキャリアになってくると、刺激が足りなくなったりもする。40歳を超え、坪倉も何か壁に直面しているような気がしてならなかった。そんなときに舞い込んできたのが、アンデルレヒトへの派遣だった。すぐに希望を伝え、家族を置いて単身、ベルギーに渡った。
ベルギーは育成改革が花開き、世界有数の強豪国に成長している。その象徴的なクラブであるアンデルレヒトでの日々は、実に刺激の連続だった。コーチ2年目からユースのアシスタントを務めたときのように。
坪倉はこう語る。
「U-10の指導から始まり、最後はU-15を教えました。日本人の指導法にも凄く興味を持っていただいて、〝きょうの90分はツボにあげるから、好きなように指導してくれ〟と任してくれたりしました。ユースダイレクターのキンダーマンスさんは〝良いものはミックスして生まれる〟という考え方で、彼らもまた新しい刺激を求めていました。〝ツボもここで良いと思ったことを日本に持ち帰ってくれ〟とも」


昼間はクラブが提携する学校に行き、クラブの選手の個人練習に付き合う。週3回、体育の授業を使わせてもらうのだ。そして夜はチーム練習で、土曜日がゲームになる。トップチームの観戦はもちろんのこと、ドイツやフランスにも頻繁に足を運ぶ。サッカー漬けの日々を送った。
ベルギーで指導者としての幅を広げた彼はチームに戻り、子供たちを指導する日常に戻った。「良いと思ったこと」は早速、指導にも取り入れているという。
「技術的、戦術的に〝こういうのもあるよ〟じゃなく、こっち側にボールを置いてとか、蹴ったらこのポジショニングを取ってとか、土台の落とし込みを徹底的にやっていたのがアンデルレヒトでした。土台にプラスして自分がやりたいこと、その土台の上で対応力を持つとか、土台を非常に大切にしていたことはとても印象深かった。
育成の指導者として20年が経ち、考え方や対応力を含めてようやく1周できたかなって思っています。これからが2周目。育成の立場からクラブ力を引き上げていかなければならないという危機感もあります。ようやく指導者として整理されてきたところがあるので、自分の与えられた役割をこなしてクラブの力になりたいと思っています」

あの日、大学をやめる報告に向かわなければ指導者の道はなかったのかもしれない。
きっと愛着あるクラブで指導者になることは運命であったのだと、坪倉は感じている。
F・マリノスのDNAを受け継ぎ、発展させていく。
それが「2週目」に入った坪倉の使命であることは言うまでもない。


二宮寿朗Toshio Ninomiya
1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載
